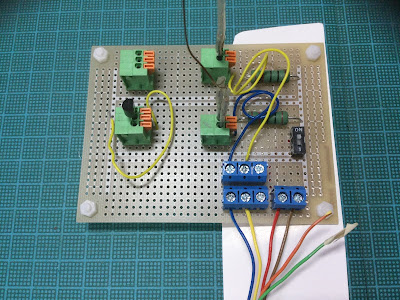改善 表示件数を制限しました
おおよそ1時間分の件数を表示するように、バッチプログラムを書き換えました。 現在は、2時間分を表示するようにさらにバッチプログラムを変更しました。
これで、それほどにスクロールせずに最新データを見ることができました。
1件のデータが34バイトです。
2時間は120分です。120分を5分で割ります。 120/5=24 件を表示すればよいわけです
バッチプログラムの詳細をここに載せます。2本のバッチファイルで一連の動作をします。
バッチファイルから他のバッチファイルを呼び出して実行しています。
(参考) REM これはコメント注釈として扱われます。
1本目のバッチで無限に繰り返し処理をさせます。
2本目のバッチで指定容量に達したらそのファイルを一旦削除させます。
そして、新たに1件目より書きます。
5分ごとに行いますので、「ハードデスクいじめ」かもしれません。
REM ===以下 1本目=== log2.bat =========
:START
@echo off
echo Hello Tom
echo 295[sec] interval logger. eternally
cd C:\Users\*****\Documents\MyRuby
C:\Users\*****\Documents\MyRuby\NTC.rb
Copy C:\Users\*****\Documents\MyRuby\2_data_NTC_current.txt C:\Users\*****\OneDrive\temperature\current_temperature.txt
timeout 297 /NOBREAK > NUL
REM 300--> 5min
REM 600-->10min
call delete.bat
GOTO START
REM ======以上 1本目 ===================
REM ==== 以下 2本目 delete.bat ======================
cd C:\Users\*****\Documents\MyRuby
REM for %%fin(*.log) do if %%~zf GTR 646 del "%%f"
for %%f in ( 2_data_NTC_current.txt ) do if %%~zf GTR 374 del "%%f"
REM もし3行表示を設定するなら 34x3-34=34x(3-1)=68 byte の条件を入れる
REM 20行表示を考えるなら Data 1件 34byte 34x20-34=34x(20-1)=646 12行表示 34x(12-1)=374 1時間分である
exit /b
REM =====以上 2本目 =======================